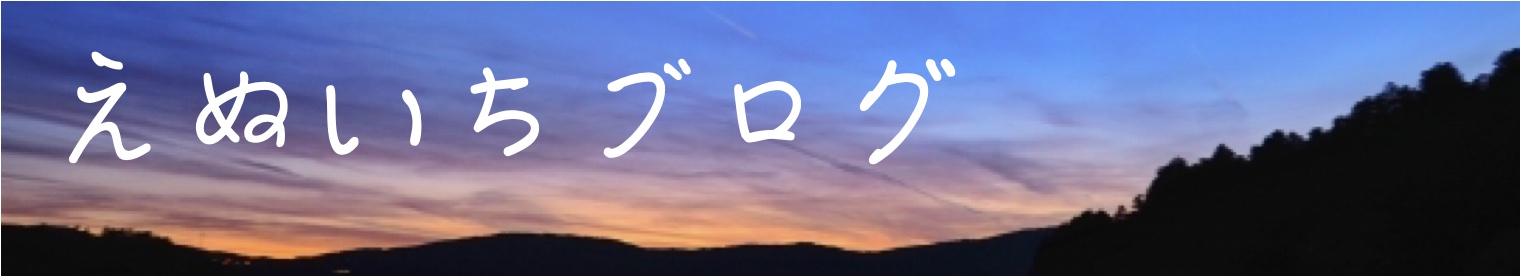この記事のもくじ
この記事では直接的に書籍の内容に触れることはできるだけ避けたうえで、読んでその内容について思ったことなどなど紹介します。
今回紹介する本
『安楽死・尊厳死を語る前に知っておきたいこと』です。
最近テレビやネットのドキュメンタリー番組で安楽死・尊厳死を扱っている機会が増えたように感じます。安楽死と尊厳死の違いは本書でも明確にはしておらずセットで論じていますが、広義の安楽死の違いについて本書より引用します。
- 積極的安楽死:医師が致死薬を投与して死なせること
- 医師幇助自殺:医師が致死薬の処方までして、患者が好きな時に服用する
- 延命治療の手控え、中止:人工呼吸器はつけないとか、透析をしないといった選択をイメージ
日本でも「ただ単に生き延びさせるだけの人生に何の意味があるのか」「生きる権利があるように、苦しませながら生かすのであれば個人の意思で死ぬ権利も認められて然るべきだ」こういった理由から上記で言う積極的安楽死を認めるべきとの意見が出つつあります。
本書は定義がはっきりしていない安楽死・尊厳死についてそもそも現代社会では何を指しているのか、どういった観点の議論がなされているのは著者自身の安楽死・尊厳死に関する意見も交えた1冊です。
本書の構成は以下の通りです。
- 安楽死・尊厳死の議論が混乱する理由(定義が曖昧という上述の背景)
- 安楽死・尊厳死という言葉が意味する行動、ではなくイメージ
- 安楽死・尊厳死のいい面だけを見る問題点
- 人の命の所有権とは
安楽死・尊厳死に関する著者の懸念事項
本書を読むまで安楽死や尊厳死は前向きな概念であると思っていました。今もそう思っている方が過半数だと思います。
ただし、著者はいい面だけ捉えるのはよくないと諭します。そもそも安楽死や尊厳死がいいと思われる背景を含めて次のように述べています。
- 安楽死や尊厳死は特定の行為ではなくて「いい」イメージを与える言葉として使われている
- 孤独死や事故死といった言葉の対比として用いることで「いい」イメージが植え付けられている
- 病気は治るか治らないかの2択で語られるために生まれている概念(治らないなら安楽死)
加えて、これは安楽死や尊厳死を推進する方も懸念事項として把握されていますが、もし法的に認めらられるようになるといくら本人の承認など条件を設けたところで「生きたいと思っているのに半ば強制される形で安楽死に至る事例が生じないか」「周りからは言われていないが忖度して死を選ぶ」といったことが起こりかねません。
これは考え方によりますが、自分は行き過ぎた安楽死・尊厳死信仰は一種の優生思想、つまり元気な人、社会にとって価値のある(税金を納めてくれるとかボランティアなどのマンパワーになる)人だけを生かしておこうという考えに繋がりかねないと思っています。
導入するなら厳重な仕組み化が必要

この本のいいと思ったところ
- 人とは違う意見で、考えを改める一助となる
- 海外の実施状況、医療の問題点について理解が深まる
特段の理由がなければ安楽死・尊厳死を否定する人はいないでしょうが、こうして一石投じる意見があることで法整備されるとしても有効に機能する仕組みになって
- 使いたい人は使う
- 使いたくなければ使わない
こういう当然そうあるべき運用になり得ます。
本書の内容に関連して思ったこと
0か100かで言ったら導入はしたらいいと思います。今の日本ではできないのでやむなく海外に行かれる方もいますが、お金もかかりますし遺骨を持って帰れないために散骨している事例を見たことがあります。
上述したようにただ導入するだけだと助かる見込みが現時点でないとされる人は全員安楽死を選ぶべきみたいな思想が生まれかねませんし、患者本人が心からそう希望したという前提下で実施されるような厳格管理が求められます。
こればっかりは実際にそういう立場になってみないと安楽死してしまいたいかどうかの考えにも至らないので今喋っててもしゃあないのですが、考えを巡らすだけでもそうなった時の心の準備にはなるのではないかと思っています。
この本のおすすめ度と読むのがおすすめな人
おすすめ度は10点満点中10点です。
この本は次のような方が読むのにぴったりと思います。
- 安楽死・尊厳死について詳しく知りたい
このような本を通じて、活発な議論が行われてほしいですね。